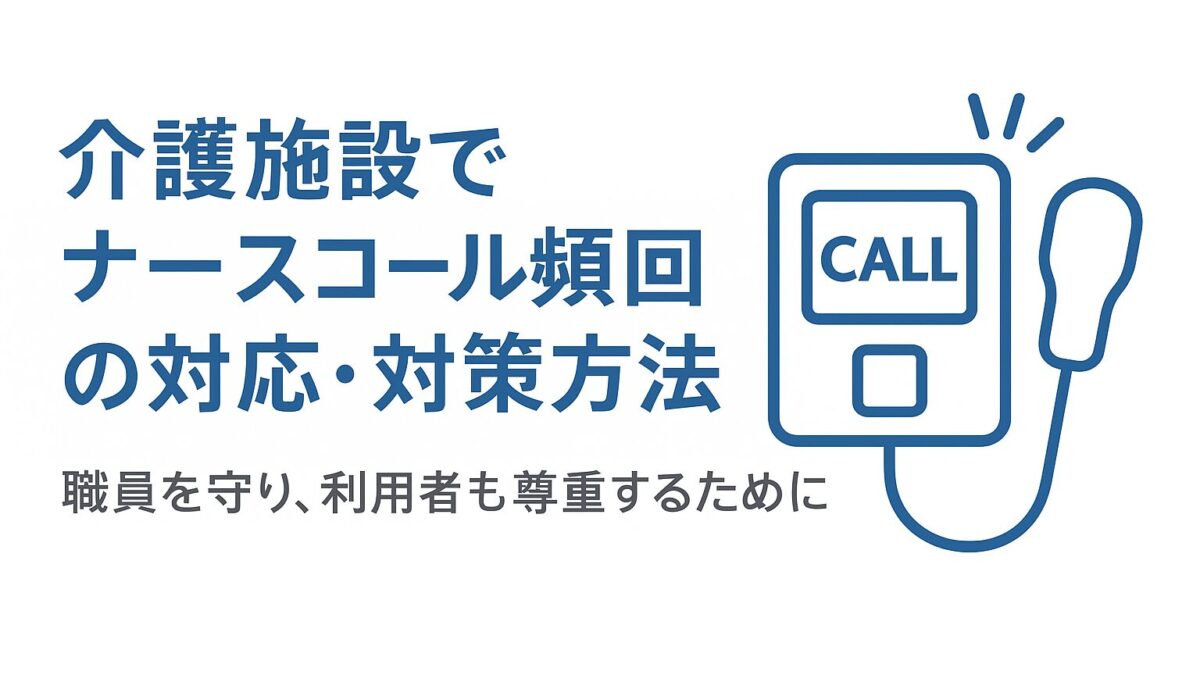
介護施設で働く職員にとって、ナースコールの頻回対応は大きな課題のひとつです。限られた人員で多くの利用者をケアする中、一人の利用者が何度もナースコールを押し続けることで、他の利用者の支援が遅れてしまい、職員の心身的な負担が蓄積されていきます。さらに、ナースコールへの対応が不十分と判断されれば、高齢者虐待と見なされる可能性もあり、現場は常に対応に慎重さを求められます。本記事では、ナースコール頻回の背景や適切な対応方法、虐待とされないためのリスク管理まで、介護現場で実践できる対策を詳しく解説します。
目次
ナースコール頻回利用の背景と現場の課題
ナースコールを頻繁に押す利用者の行動には、単なる「わがまま」や「困らせたい」という意図があるわけではありません。その多くは以下のような要因から発生しています。
- 不安や孤独感(特に夜間)
- 身体的な違和感(痛み・かゆみ・尿意など)を言語化できない
- 認知症による時間感覚の喪失
- 自分の意思に反してナースコールを握ったり押したりしてしまう
- 「押せば来てくれる」という学習(条件づけ)
- 生活リズムの乱れや昼夜逆転
現場では、頻回に押されることで対応に追われ、他の利用者のケアが遅れてしまい、職員が罪悪感やストレスを抱えることもあります。しかし、ナースコールを取り上げる・押せないように隠すといった行為は、虐待や介護放棄にあたる可能性があり、慎重な判断が必要です。
ナースコール頻回対応の具体的な対策と工夫
| 対策の種類 | 内容 | 注意点・メリット |
|---|---|---|
| ナースコールの種類の見直し | 握りしめてしまう場合は、押しボタン式やタッチ式に変更。誤作動の予防にも。 | 取り外しは不可。機能を残しつつ誤使用を防ぐ形で工夫することが虐待防止に重要。 |
| コールが押された理由の記録と分析 | 頻回利用者に対し、何時・どんな理由で押されたかをスタッフ間で共有。記録から原因の傾向を把握。 | 行動記録を通じて「不安」「寂しさ」「排泄前後の習慣化」などのニーズの把握と予防策立案に役立つ。 |
| センサーマットや声掛けの併用 | 起き上がり・排泄などのタイミングを事前に察知し、スタッフから声かけを行うようにする。 | コールを押す前に関わることで、安心感と信頼形成につながる。利用者の主体性も尊重される。 |
| 心理的な安心の提供 | 「あとで来ます」ではなく、「〇分後に来ます」と具体的に伝え、予測可能性を与える。 | 声かけの言い方ひとつで不安を減らすことができる。事前にスケジュールを共有することも有効。 |
| 職員の交代ルール整備 | 頻回対応者にはチームで順番に対応し、一人に負担が集中しないようにローテーション制にする。 | 感情的な対応や疲弊によるトラブルを未然に防げる。記録と申し送りの徹底がポイント。 |
ナースコールを押せない場所に置くは可能なのか?
原則として、ナースコールを利用者の手の届かない位置に置くことは「不適切な身体拘束」に準ずる行為とされることがあります。理由や記録なしにナースコールを外す・隠す・無効化することは、「意図的な介護放棄」と判断されるリスクがあります。
どうしても安全上の理由や認知症による誤作動が頻発している場合には、「多職種での検討」や「記録とモニタリングの実施」が前提となります。具体的には以下のような対応が望まれます。
- 家族への説明と同意の取得
- 担当医やケアマネジャー、施設長など多職種での記録付き検討
- 「一定時間だけ外す」「見守りの強化とセットで対応」などの代替措置
ナースコール放置が「虐待」とされた事例
実際に、以下のようなケースで「虐待」と判断された事例があります。
事例:夜間ナースコールに応じなかったケース(厚労省虐待調査より)
- 認知症のある高齢者が夜間に頻回にナースコールを押す
- 職員が「またあの人か」「無視しておいて」と言い合い、対応せず放置
- 翌朝、利用者がベッドから転落して骨折
- 調査の結果、「故意の無視」が虐待にあたるとして行政処分
このような事例では、「対応できなかった」ことよりも、「組織として無視する体制を黙認していたこと」が問題視されました。
このように、ナースコールが頻回だとしても、その場で無視をするという判断はせず、どんな状況で何時にナースコールがあり訪問するとどんな状態だったのかを記録に残した上で、その対策として関係者みんなが知恵を出し合った上で、みんなが合意していくことが大切です。特に夜勤帯にこのようなことが起きると、数人の職員ではどうにもならなくなってしまうことも想定されますが、できる限り記録に残し、可能な範囲のことを対応していたということは示せるようにしましょう。その上で、頻回の対応について施設全体で考え、家族や場合によっては自治体などにも確認をしながら進めましょう。
現場で無理なく、虐待とされないためにできること
「現場で無理なく、虐待とされないためにできること」は、介護職員一人ひとりの努力に依存するのではなく、組織としての体制づくりが鍵となります。まず大切なのは、頻回にナースコールを押す利用者に対して、すべての職員が「その人がなぜコールを鳴らしているのか」という視点を共有できるようにすることです。日々の対応記録だけでなく、ナースコールの回数や押された時間帯、理由などを記録してチームで可視化し、対応の傾向や必要な支援を客観的に見直せるようにしておくと、属人的な感情に左右されない対応が可能になります。
また、記録された情報をもとに、定期的にミーティングやケース検討の時間を設け、現場の声を拾い上げることも大切です。職員の中には「こんなことで相談していいのか」と感じてしまう人もいるため、管理者やリーダーが積極的に意見を聞き、現場のストレスや疲労感が表面化する前に対策を講じる姿勢が求められます。たとえば、頻回コール対応者については、職員間で順番に担当を交代する仕組みを整え、特定の職員に負担が集中しないようにすることが効果的です。
さらに重要なのが、施設全体で「ナースコールの回数を減らすこと」を目標とするのではなく、「利用者が安心して過ごせる環境をつくること」を目的にする視点です。呼ばれる前に声をかける、事前に予定を伝える、孤独を感じやすい時間帯に話し相手をつけるなど、小さな取り組みの積み重ねがコールの回数そのものを減らす効果につながることもあります。
職員が疲弊しないための仕組みづくりと、利用者の尊厳を守る支援。この両立こそが、介護の現場において虐待とされない支援体制を築くための最も確実な道といえるでしょう。
おわりに
ナースコールの頻回対応は、現場の職員にとっても、他の利用者にとっても大きな負担です。しかし、単に回数を抑えることが目的ではなく、「なぜ押すのか」「どうすれば安心できるか」を考えることが、真の支援になります。
そして、対応しきれないことを“職員の責任”にするのではなく、「仕組み」と「体制」の見直しによって、無理なく支え合えるチームケアを築くことが、虐待を防ぎ、すべての利用者と職員の安心につながる道です。
