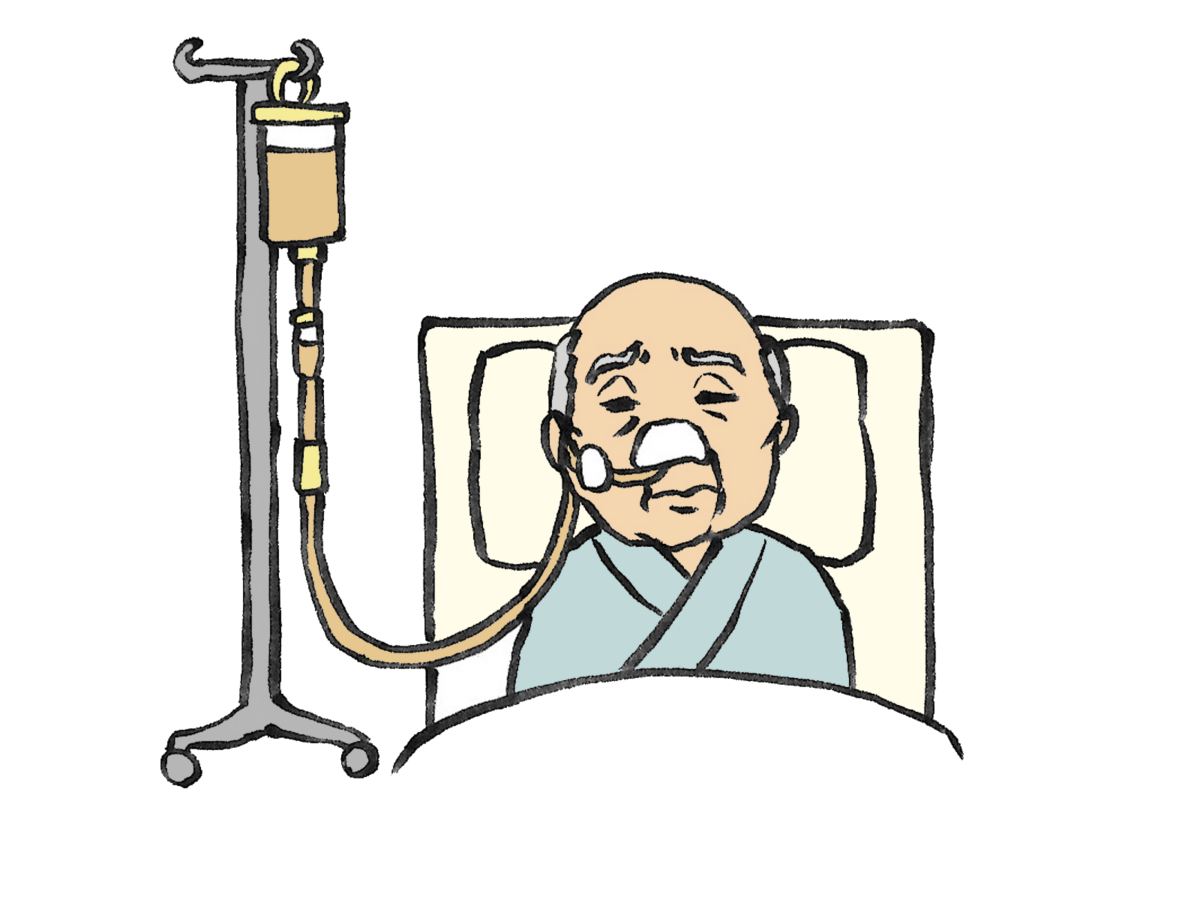
経管栄養は、口から食事をとることが難しい利用者に対して、鼻から胃に入れたチューブや胃ろう・腸ろうを通して栄養を投与する方法です。延命治療の一種として近年は減少傾向にありつつも、介護の現場では経管栄養の状態になっている利用者は多く、介護職員が関わる場面も少なくありません。
厚生労働省の通知(令和4年12月1日「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」)では、経管栄養に関連する一部の行為が「医行為にあたらない」と整理されました。これにより、介護職員が安心して担える部分と、医師や看護師に任せるべき部分がより明確になっています。ここでは、介護現場での対応をわかりやすく解説します。
目次
経管栄養とは?
経管栄養とは、食べ物を口から十分に摂取できない人に対して、胃や腸に直接栄養を送り込む方法です。誤嚥性肺炎や神経疾患による嚥下障害、手術後の回復期など、経口摂取が困難または不十分な場合に選択されます。利用者の状態や期間、予後を考慮し、医師の判断で方法が決定されます。
大きく分けて「経鼻胃管栄養」と「胃ろう・腸ろうによる栄養」の2種類があります。
経鼻胃管は比較的短期間の栄養補給に使われ、チューブを鼻から胃に通して栄養剤を注入します。一方、胃ろうや腸ろうは腹部に直接小さな穴を開けてチューブを留置する方法で、長期的に栄養を必要とする人に用いられます。経管栄養は命を支える重要な手段であり、医師・看護師・介護職員が連携して安全に行うことが求められます。
経管栄養の種類と特徴
| 種類 | 方法の概要 | 主に選択される場面 |
|---|---|---|
| 経鼻胃管栄養 | 鼻から細いチューブを胃まで挿入して栄養を注入 | 短期間の栄養補給、回復期、嚥下機能改善が見込まれる場合 |
| 胃ろう(PEG) | 腹部から直接胃に小さな穴を開けてチューブを留置 | 長期間の栄養補給が必要な場合、嚥下障害が慢性的な場合 |
| 腸ろう(PEJ) | 腹部から腸に直接チューブを挿入して栄養を注入 | 胃に問題がある場合や胃ろうが使えない場合 |
胃ろう(ペグ)・経鼻胃管栄養・中心静脈栄養の違いと注意点
介護職員ができること
経管栄養において介護職員ができるのは、注入そのものではなく、あくまで周辺的な準備や片付けです。
例えば、あらかじめ利用者に留置されている経鼻胃管チューブを固定しているテープが外れたり汚れたりした場合に、決められた位置に再度貼り直すことは認められています。この場合でも、皮膚に赤みやただれがなく、専門的な判断を要さない状態であることが前提となります。また、注入用の栄養剤を準備したり、終了後に使用器具を洗浄・片付けしたりすることも介護職員の業務として可能です。こうした作業は、安全に行えば医行為には当たらず、介護の一環として位置づけられています。
介護職員ができないこと
一方で、経管栄養の中心となる「注入」や、注入中に行う医学的判断は介護職員には認められていません。具体的には、経鼻胃管の先端が胃に確実に留置されているかどうかを確認すること、胃ろうや腸ろうの周囲に炎症や肉芽が生じていないかを観察すること、注射器で内容物を吸い上げて胃や腸の状態を評価することは、いずれも医師や看護師が行うべき医行為です。これらは医学的知識や経験を必要とし、誤った判断が生命に危険を及ぼすため、介護職員が行ってはいけない領域です。
介護職員が経管栄養を注入できる条件について
経管栄養の注入は原則として医師や看護師が行う医行為です。しかし、厚生労働省の通知では、本人や家族の同意を得たうえで、特別な研修を修了した介護職員が「日常生活で継続的に必要な医療的ケア」として対応できる場合があります。これは主に胃ろう・腸ろうからの経管栄養に限られ、経鼻胃管栄養の注入は医行為として看護師が行うべきものとされています。
具体的には、喀痰吸引等研修の「経管栄養に関する基本研修」を修了した介護職員であることが前提条件となります。さらに、医師や看護師が個別に手順を指導し、本人や家族と合意が形成されていることが求められます。
加えて、その介護事業所が研修を終了した介護職員が喀痰吸引や経管栄養の行為を行うことについて届出していることも必要です。たん吸引等の従事者認定及び事業者登録、たんの吸引等(認定特定行為業務)従事者の認定証交付申請などです。
研修を終了している介護職員だとしても、事業所として届出・登録していない場合には認められないものです。
護職員が自己判断で注入を開始することは認められておらず、利用者の体調やろう孔部の状態確認は必ず看護師が行った上で、介護職員が補助的に関わる形となります。
つまり「注入できる条件」とは、胃ろう・腸ろうに限り、介護職員が研修を修了していること、看護師の指導・監督下にあること、事業所が届出・登録してあること、本人や家族の合意があることという5つの柱が揃っている場合です。この条件を満たさない場面では、注入は介護職員の役割には含まれません。
看護師を呼ぶべきタイミング
介護職員が経管栄養に関わる中で重要なのは、異常をいち早く察知し、看護師に引き継ぐ判断を行うことです。例えば、チューブを固定する皮膚に赤みやただれが見られる場合、貼り直しをせずに看護師に報告する必要があります。
また、胃ろうや腸ろうの周囲に浸出液や出血がある場合、利用者が苦しそうにしている場合、注入中に咳き込みや吐き気を示した場合も、介護職員が独自に対応することはできません。こうした場面ではすぐに看護師を呼び、医療的判断を仰ぐことが利用者の安全を守る行動となります。
経管栄養の準備と片付けの流れ(手順の例)
準備段階
-
利用者の体調を観察し、普段と変わった様子がないかを確認する
体調不良や苦しそうな表情がある場合は、介護職員が対応せずにすぐ看護師に報告する。 -
手指を清潔にし、必要な器具(注入用のボトルやシリンジ、経腸栄養セット、手袋など)を準備する
ここまでの器具の準備や衛生管理は介護職員が行える。 -
経鼻胃管の固定テープが外れたり汚れている場合、皮膚に発赤やただれがなければ、決められた位置に貼り直す
赤みやただれがある場合は貼り直しをせず、看護師を呼ぶ。 -
栄養剤を注入できる状態に整えたら、看護師に連絡する
実際の注入行為は必ず看護師が行う。
注入中
-
注入そのものは看護師の業務であり、介護職員は行わない。
-
介護職員はそばで見守り、利用者の状態に変化(咳き込み、嘔気、顔色不良など)があれば直ちに看護師に知らせる。
終了後の片付け
-
注入が終わったら、看護師が栄養剤の流れを止め、チューブを閉鎖する
介護職員は勝手にチューブを外したり栓を抜いたりしてはいけない。 -
看護師がチューブやボタンの状態を確認した後、介護職員が器具を洗浄する
シリンジやボトルの洗浄・乾燥・整理などは介護職員が担う。 -
作業後は利用者の体調を再度確認し、普段と異なる様子があれば速やかに看護師に報告する。
ポイント
経管栄養に関わる介護職員の役割は「準備」「片付け」「見守り」に限定される。チューブの位置確認や注入、終了操作はすべて看護師が行う。利用者に少しでも異常がある場合や皮膚に変化がある場合は、自分で判断せず必ず看護師を呼ぶことが安全につながる。
まとめ
経管栄養において介護職員ができることは、あらかじめ決められた位置でのテープの貼り直しや、栄養剤や器具の準備と片付けにとどまります。注入行為やチューブの位置確認、皮膚や胃腸の状態評価といった医療的判断は、必ず看護師や医師が担うものです。介護職員は、自分に任された範囲を正しく理解し、異常があれば速やかに看護師に引き継ぐことが求められます。その役割を徹底することで、利用者にとって安全で安心できる経管栄養の実施が支えられるのです。